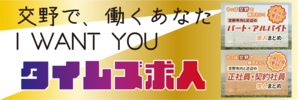岩でっか! 12mの巨岩が御神体!磐船神社はこんなところ〜交野市で天孫降臨伝説が今なお語りづかれている神社〜
天孫である邇邇芸命(ににぎのみこと)が降り立った天孫降臨の場所として有名なのが九州の高千穂で天孫降臨といえばこのことだ!というのがメジャーな話だと思います。
が、
実はもう1つ、天孫降臨伝説が語り継がれているスポットがあります。
そう、それが交野市私市9丁目にある磐船神社です。
(神社正面の入り口のところに、天孫降臨の地って書かれている)
高さは12mくらいある大きな岩が御神体。
磐船神社御由緒
厳かな雰囲気があり、かつ、ここは天孫降臨伝説がある神社です。高さは12mくらいある大きな岩が御神体。
磐船神社御由緒
「日本書紀」や「古事記」、「先代旧辞本紀」などの古い書物によりますと、天孫饒速日尊(ニギハヤヒノミコト)は天照大御神(アマテラスオオミカミ)の御孫神にあたり、大御神の御勅命により高天原より天の磐船に乗って河内国河上哮が峰に降臨されました。のちに大和国に入り、大和河内地方を開発し建国の礎を築かれ、人々より天津神(天より来られた貴い神様)と崇敬された神様であります。
また、饒速日命が降臨に際して、天空より国土を望まれ「虚空見つ日本国(ヤマトノクニ)」と言われた事が「やまと」という国号の始まりとされています。
尊は高天原より持って来られた十種瑞神貢により鎮魂祭を行い、病に苦しむ人々を助け、死人をも蘇らせたと云われ、加持祈祷の根元として神道のみならず修験道、密教、陰陽道からも崇敬されて来ました。
尊の子孫は物部氏と呼ばれる古代大和朝廷における最大最強の氏族を形成し、大連(おおむらじ)として代々の天皇に仕えており、ここ交野の地には肩野物部という一族がおりました。
当神社は、饒速日尊が乗って来られた天の磐船を御神体として祀り、古来より天孫降臨の聖地として崇敬されています。
当神社の創祀年代は詳らかではありませんが、磐座信仰という神道最古の信仰形体と伝承の内容から縄文から弥生への過渡期まで遡ると考えられています。
その後、物部氏を中心として祭祀が行われていましたが、物部氏本宗の滅亡後、山岳仏教や住吉信仰などの影響を受けるようになり、平安時代には「北嶺の宿」と呼ばれ、生駒山系の修験道の一大行場として変貌を遂げるに至り、境内には四社明神の石仏や、不動明王像が像が祀られ、弘法大師の作とされる磐船和讃伝承されています。
今でも神仏習合を色濃く残しており、例大祭には護摩檀を設けて大焚祭が行われています。
また、当社大岩窟は、古来より行場として知られ、現在でも多くの行者や拝観者が訪れます。
また、饒速日命が降臨に際して、天空より国土を望まれ「虚空見つ日本国(ヤマトノクニ)」と言われた事が「やまと」という国号の始まりとされています。
尊は高天原より持って来られた十種瑞神貢により鎮魂祭を行い、病に苦しむ人々を助け、死人をも蘇らせたと云われ、加持祈祷の根元として神道のみならず修験道、密教、陰陽道からも崇敬されて来ました。
尊の子孫は物部氏と呼ばれる古代大和朝廷における最大最強の氏族を形成し、大連(おおむらじ)として代々の天皇に仕えており、ここ交野の地には肩野物部という一族がおりました。
当神社は、饒速日尊が乗って来られた天の磐船を御神体として祀り、古来より天孫降臨の聖地として崇敬されています。
当神社の創祀年代は詳らかではありませんが、磐座信仰という神道最古の信仰形体と伝承の内容から縄文から弥生への過渡期まで遡ると考えられています。
その後、物部氏を中心として祭祀が行われていましたが、物部氏本宗の滅亡後、山岳仏教や住吉信仰などの影響を受けるようになり、平安時代には「北嶺の宿」と呼ばれ、生駒山系の修験道の一大行場として変貌を遂げるに至り、境内には四社明神の石仏や、不動明王像が像が祀られ、弘法大師の作とされる磐船和讃伝承されています。
今でも神仏習合を色濃く残しており、例大祭には護摩檀を設けて大焚祭が行われています。
また、当社大岩窟は、古来より行場として知られ、現在でも多くの行者や拝観者が訪れます。
と説明がありました。
興味ありましたら、ぜひぜひ。
近くにはほしだ園地の星のブランコやログハウスカフェのおじいさんの古時計などもありますよ。
記事:ハラダ
ハラダのこれまでの記事はこちら