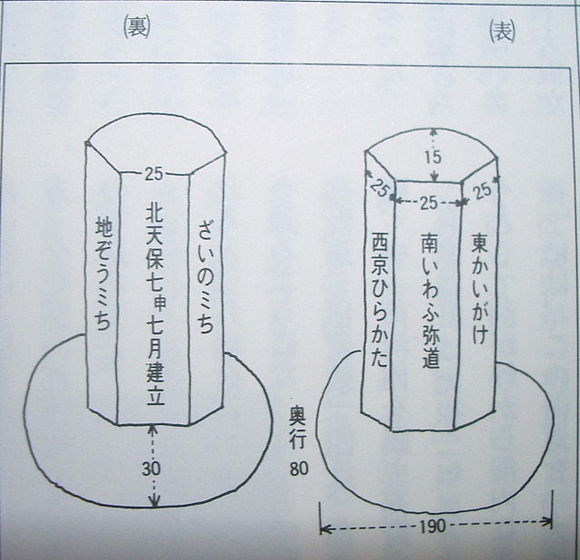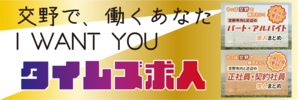磐船街道沿いにある『大松の辻の六角形の道しるべ』はなんと江戸時代からある!〜今から186年前にできた歴史あるもの〜
大きな道標や石灯籠がある
こちらの道を進むと京阪河内森駅です。
こちらに行くとJR学研都市線の踏切に向かい消防署に向かう道です。
幾度となくこの道を通っているのですが、ふっと気になってしました。
文字が入っているので道しるべらしいのですが、なんて書いてあるんでしょう。
変わった形だなっと上から撮ってみると六角形。
六面それぞれに文字がありました。
正面左側
正面右側
後ろの文字
ずっとここにあるもののようなので、重要な物、あるいは大切な物なのだと思われます。
交野の歴史のことはここを見よ!
と頼りにさせて頂いているゴッドファーザー交野さんの『星のまち交野』のホームページにやはり、これについての記載がありました。
2009.6.13の交野鼓動を歩くシリーズ 磐船街道が詳しく載っています。
(画像クリックで星のまち交野の該当ページへ)
この道標がある通りは、磐船街道とかいがけの道の分岐点の様です。
そして、この六角形の道標にはこう書かれていると、星のまち交野で説明がありました。
(画像引用:星のまち交野「古道を歩く 磐船街道」のページより)
正面から「南いわふ弥道」
右に「東かいがけ」
左「西京ひらかた」
真後ろは
「北天保七申七月建立」
右「ざいのミち」
左「地ぞうミち」
と書かれているそうです。
天保7年は、1836年。
今年が2022年ですから、186年前に設置されたものなんだそうです!
186年前は江戸時代ですね。翌年1837年に大塩平八郎の乱のがあったと出てきました。
詳しくは先に紹介した「星のさと交野」に書いてありますが、すごーーーーく古いものだそうですよ。
これを、大切に残してくれた方に感謝ですね。
記事:ひろちゃん
撮影:ひろちゃん
取材場所:私市2丁目
ひろちゃんのこれまでの記事はこちら