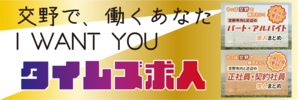住吉神社の本殿前に『茅の輪』が登場してるみたい!
いつで建てられたのか不明

その建立は何年の何月何日と定かにはわかっていないようですが、交野市はその昔、肩野物部氏という物部氏の流れを組む豪族がいた土地でして、また縄文時代や弥生時代の遺跡やもっとさかのぼれば2万年前くらいの石器時代の遺物が出土していたりと、交野の歴史はそれはそれは古いので、
私部の住吉神社がいつできたのか?
とよくわかっていないということは、きっと相当前からこの神社はここにあった理由ということなんだと思います。
住吉神社の大鳥居

住吉神社には大きな石でできた鳥居があって、それは高さ2丈4尺(約7.3m)。
今から150年以上も前の1860年(万延元年)に建てられたそうです。
この大きな石は交野の山から切り出されて住吉神社の氏子が総出で運び出したそうな!
かなり大掛かりな作業です。
そんな古くから交野にある住吉神社。
6月30日から茅の輪が登場しているみたいです!
デデーンっと本殿前に茅の輪

茅の輪の横には説明書きがあってその由来やくぐり方なんかも教えてくれています。

住吉神社のホームページの年中行事が掲載されているページには、大祓というのがあって、茅の輪くぐりが6月の行事とありました。
(画像クリックで住吉神社ホームページへ)
なお、この住吉神社の茅の輪。
7月の行事の半夏生祭の湯立て神事の時にも飾られているようなので、ちょっとの間はきっと茅の輪くぐりができるんと思います。
住吉神社の茅の輪くぐりもいつからやってると分からない行事なのかもしれませんが、きっと遥か昔からほとんど変わることなく繰り広げられているものなんじゃーないでしょうか。
その瞬間瞬間、1日1日の生活の中で「今」を感じることが多い中で、まちの中をちょっと見渡すと脈々と続いている何かがたくさんあって、そーいうのがきっとまちのアイデンティティにもなっているのかもしれません。
【住吉神社】
私部に昔からある神社、住吉神社の関連記事はこちら!
(画像クリックで住吉神社関連記事一覧へ)
ハラダ@交野タイムズ
(記事中、茅の輪くぐりの写真はフェイスブックの交野シェアのご投稿写真をお借りさせて頂きました)